
上古の日本の姿を知りたいと思った時、まず史料とすべきものは8世紀の記紀となりますが、当然それらが編纂された時代以前の歴史は、各氏族間に何世紀も語り継がれた神話や伝承となります。もっとリアリティのある史料を求めると、中国史料を参考にするほかないのです。
その中でも、いわゆる魏志倭人伝は、つとに有名ですが、これは『三国志』の「魏書」の「東夷伝」の中の「倭人」条で、文字数では三国志全体の0.5パーセントにしか過ぎないのです。したがって、歴“史”研究の基礎である「史料批判」のためには、三国志全体の中で倭人伝がどのような位置づけなのか?陳寿の人物像や学問、中国や中国正史や皇帝制度に対する知識など、幅広い視点が必要なのですが、それらは殆どの場合スルーされ、内容に対する無批判を前提とした解釈合戦が繰り返されています。そのそもそもの勘違いの元が「正史」という言葉の響きによるものです。
たとえば、中華人民共和国外交部長の王毅氏などは、昔からそのふてぶてしい態度と発言で日本人をはじめ関係国をムカつかせてきましたが、それは彼の人格や能力のせいではありません。(たぶん)
彼が内面どんなことを思いどんな知見を持っているか、というようなこととは関係なく、あのような振る舞いをするからこそ(もちろんほんの一要素ですが)彼の国で長らくあのポジションを独占していられるわけです。
中国にとって「何が正しいか」は、それが「中国にとって正しいかどうか」であって、視線は常に内向きなのです。つまり、中国共産党に、その思想・能力・言動がどう評価されるか、が全てで、相手国・他国の反応は関係ないということです。
実は中国正史も同じことで、史実を後世に(元より他国になど)伝える目的で当時の情報を正確に記した歴史書、などでは決してありません。
「正史」の意味が「正しい歴史」「中国王朝がその内容を正確であると認定した史書」であると勝手な勘違いをしている人が未だに多いのです。
「正史」とは、「中国の正統を記した史書」であり、ざっくばらんに言えば「その史書を記す人物が、自分が仕える皇帝が本物の天子である」ことを、あらゆる角度から説明した書物であり、それが唯一最大の主旨なのです。
そのために必要ならば、当然、話を盛ってでも書くし、都合の悪いことは隠すのです。もちろん数字も操作します。
中国の「正史」は「天下は皇帝のもとに不変のもの」という中国皇帝の正統を述べるものです。まずは神話時代において、黄帝以来の五帝が天子となり天下を統治した、という「正統の観念」が作られました。
これを「伝統」といいます。
夏・殷・周・秦の時代になり、天子の位は「放伐」(ほうばつ)によって「敗者から奪われ勝者に与えられるもの」となります。
この「天命を取り去り革(あらた)める」ことを「革命」といいます。
早い話が「何でもあり」で、日本人からすれば「天命とは何ぞや?」という感じですが、司馬遷にしてみれば、そういうレトリックを使う以外に手はなかったのです。
何故なら、自分が仕える漢朝は、成り上がりの高祖によって開かれているのですから「実力でトップに上りつめた者に後から天命が下る」と「正統」を規定するのは当然です。つまり中国においては「革命」こそが「天命」だということができます。
後に書かれた正史は、その記述法だけでなく、記述の目的も同じであり、例えば三国志を書いた陳寿は、自分が仕える西晋の皇帝・司馬炎が、いかに正しい統治者(天子)であるかを書くために、三国時代においては「魏」こそが正しい中国であり、その重臣・司馬懿が魏で最も秀でた人物だったことを特筆大書したわけです。
中国正史というものは、このように限りなく自己中心的で、不正確な記述もを含む政治色の強い書物なのでした。現在では「中華人民共和国」のおかげ?で「中国」というものに対する日本人の幻想は限りなく消えつつありますが、つい最近までは中国の歴史や文化に対する根強い羨望を多くの日本人が抱いていました。

ところで、過去記事の中で、中国正史に記される「国」の意味について、あれこれ書いたのですが、これには納得のいかない人も多いのではないか?と、今更ながら気付きました。
何故か?というと、いくら「国」が「都市」や「村」のことだと説明したところで、「あの陳寿が書いた正史のタイトルは『三国志』じゃないか!」思うのが普通だわな、と思い至ったわけです。つまり、『三国志』は「魏」「呉」「蜀」を「国」と表現しているではないか!ということです。
この点は中国史の専門家も誰も指摘しない(というか魏・呉・蜀だから三国なんでしょ、で思考停止か?)ので、私の意見を述べておくことにします。
たとえば、「魏呉蜀」で画像検索すると、だいたいこんな画像がずらっとヒットします。
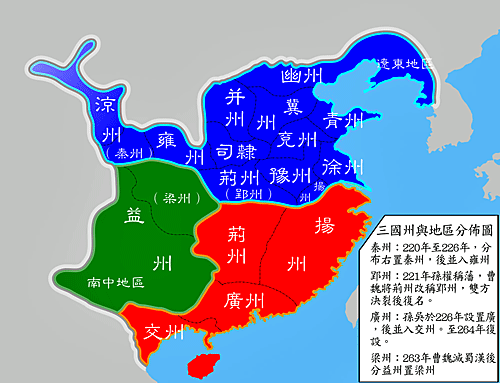
このような地図のほか、魏呉蜀の境界の曖昧な地図も多数ヒットしますが、一体どちらが正しいのでしょうか?境界線をリアルに描いている地図というのは、現在の研究によって想定されている当時の「州」の範囲を基準にしているのです。でも、漢~三国時代において、このような現代地図の如きくっきりとした境界線が引かれていたのでしょうか?甚だ疑問です。
現代人は現代の常識に従って、古代を理解しようとします。
その常識とは、たとえば、国家とは「領土国家」「国民(民族)国家」であると信じて疑わないというものです。
簡単に言えば、A国というものを考えるとき、まずその境界線(国境)を想定・規定し、その内側がA国で、その範囲内に住む人々をA国人だと考えるのです。
たとえば、中国正史の本を見ていても、原文には「◯◯県と◯県は◯◯郡に属す」とだけ書いてあるのに、その現代語訳では「◯◯県と◯県の“土地は”は◯◯郡に属す」と、勝手に内容が変えられていたりします。
つまり、「行政単位」「組織構成」の話が「行政区域」「領土構成」の話になっているわけです。(現代人には「県」を見ても「郡」を見ても「区域」としか映らないのです。 この現在では当たり前に思える領土国家の概念は、古代には世界のどこにも存在しませんでした。
国民国家とは、国家内部の全住民をひとつのまとまった構成員(=「国民」)として統合することによって成り立つ国家。
ヨーロッパは一般に「国民国家」成立のモデル地域とされており、その先進国とされるのがイギリス、フランスであった。さらに「国民国家」とは、確定した領土をもち、国民を主権者とする国家体制およびその概念を指すことがある。
※国民国家(世界史の窓)
ほぼ近代国家は国民国家に該当する。英語では、nation state という。
そして一定の国境の中に居住する人々を国民としてとらえ、「主権、国民、国境」という「国家の三要素」を持つ国家が次第に形成されていった。
ウィーン体制の時期は一時絶対王政が復活したが、1848年革命の前後にフランス・イギリスは、憲法と議会を持ち、国民が主権者である国家を形成させた(フランスは第2帝政となるがそれも国民が選出する皇帝であった)。
西ヨーロッパでは19世紀までに国民国家が形成されたが、東ヨーロッパにおいては20世紀前半の第1次世界大戦後がその時期に当たり、アジアでは日本などは19世紀に曲がりなりにも国民国家を形成させたが、多くは植民地か半植民地状態にあったため、20世紀後半の第2次世界大戦後に国民国家となっていく。
※領域 (国家)(Wikipedia)
「領域」は、広義には社会・経済地理学のタームで、絶対空間の無限の広がりを有界化してできた、空間の一片のことを指す。
この領域は経済・社会の主体の容器となり、内部ではその主体相互間に均質化の作用が及び、領域ごとに異質化された経済・社会空間が出来上がる。
狭義には、国家の主権(統治権)が及ぶ空間的領域のことを指し、領土、その周りの水域(領水、海の場合は領海)及びそれらの上空(領空)から構成される。
「領域」という概念も、上のように「空」「海」を「土地の延長」として捉えることで生まれたものですから「領土」が基本になります。
古代王朝の事を考えるときにも、殆どの場合、まずその「外枠」(国境)を求めることから始め、その中を領土と考え、次にそこに在る都市や人々へ目を向ける、というパターンになります。ところが上古の実態はその逆で、まず「核」となる人間や都市があり、その力の増大にともなって影響力の及ぶ範囲が外に向かって広がってゆくのです。
歴史上の推定人口は、日本の場合、天下泰平の世が続いた江戸時代でも約三千万人、3世紀ころは約五十万人とされています。
卑弥呼がまだ女王に即位して間もない西暦200年ころは、たとえば、四国全体では人口約3万人と推測されています。(鬼頭宏)
徳島の田舎である私の住む市は、人口約30,000人ですから、当時は四国全体で現在の田舎の一市程度の人間しかいなかったわけです。この想定人口には疑問を持つ人もいるでしょうが、だからといって10倍にも20倍にもはなりません。早い話が土地は人口比で見てスカスカだったのです。
平均的満遍に人が住むわけはなく、一部を除いては集落を形成していたでしょうから、集落と集落の間のフリーゾーンのほうが圧倒的な広さになります。
中国大陸も同じで、紀元前からBC1000年ころまでは、戦争や飢饉で人口が半減したり十分の一になったりを繰り返しながら、人口はずっと上限5~6000万人くらいです。
江戸時代の日本列島3000万人でもかなり少ないと感じるでしょうが、あの広大な大陸に5000万人、という状態がどんな様子か想像してください。
魏・呉・蜀は、人手不足を補うため、それぞれ外地で人間狩りを行っています。
当時、国家というもの自体がありませんが、領土意識などもっとありません。
領土は人が支配してこそ領土なのですが、その“人”が少なすぎるのです。
私が中学時代に読んだある本で紹介されていたエピソードに、南米某国の田舎で土地を購入しようとした男性の話があり、その購入価格は“ここからここまで”という「横幅」で決まり、「奥行き」の幅は購入者の意志で自由に選べた、というものがあったのを思い出します。
日本では、戦国時代の国盗り合戦など、歴史的にも領土意識が強かったというイメージがありますが、それは、日本の場合、国力が「石高」という米の生産量で決まっていたからです。領地が広いほど米がたくさん取れる、というのが日本の国力の経済原理でしたが、古代においては、日本も中国もそうではありません。
では、何があったのか?
それが「国(こく)」(経済都市)なのです。

経済活動の主役は「交易」で、中国の「国」とは交易市場を核とした「都市」のことであり、その「都市ネットワーク」を制することが「中国を制する」ということでした。
農業が経済の主役ならば、耕作地(領土)の広さが経済力の決め手となりますが、交易の場合は、その都市の「立地」こそが重要な要素です。中国大陸においては、古代から「中原を制するものが天下を制する」のも、そのためです。
中国人たちは、交易に適した場所を選んで「国」を造っていきました。
『旧唐書』に、倭「国」の特徴として、「其國居無城郭」其の國、居るに城郭無し、と、わざわざ記すように、中国では「国」が「城壁で囲まれている」のが当たり前で、「倭の国々にはそれがないよ。マジか倭人!」と言っているのです。
何故ならは、中国では国邑を城壁で囲まなければ異民族から略奪の目に合うというのが普通のことだったからです。
邑(Wikipedia)
殷代、東周時代の邑は君主の住まいや宗廟等、邑の中核となる施設を丘陵上に設けて周囲を頑丈な城壁で囲い、さらにその周囲の一般居住区を比較的簡単な土壁で囲うという構造のものであった。
戦時に住民は丘陵上の堅固な城壁で囲まれた区画に立てこもり防戦した。
邑は、城壁に囲まれた都市部と、その周辺の耕作地からなる。
そして、その外側には、未開発地帯が広がり、狩猟・採集の経済を営む非定住の部族が生活していた。
彼らは「夷」と呼ばれ、しばしば邑を襲撃し、略奪を行った。そのために存続が難しくなった小邑は、より大きな邑に併合された。
さらに春秋時代の争乱は、中小の邑の淘汰・併合をいっそう進めた。
大邑による小邑の併合や、鉄器の普及による開発の進展のために、大邑はその領域を拡大してゆく。
こうして、春秋末から戦国にかけて、中国の国の形態は、都市国家から領土国家へと発展していった。
ここでも、「領域を拡大」「都市国家から領土国家へと発展」とありますが、それはもっと後の時代のことでしょう。何故なら、その後、秦の始皇帝が統一したのは中国の「領土」ではなく、中原に点在した「国々」(複数の城郭都市)だからです。
中原(Wikipedia)
狭義では春秋戦国時代に周の王都があった現在の河南省一帯を指していたが、後に漢民族の勢力拡大によって広く黄河中下流域を指すようになり、河南省を中心として山東省の西部から、河北省・山西省の南部、陝西省の東部にわたる華北平原を指すようにもなった。古代でいわゆる「中国」や「中州」と同義で、異民族から隔てられる文明の中心地という意味があった。その後、南方へと発展していった漢民族にとって中原は民族の発祥の地とされてきた。
秦漢(Wikipedia)
秦漢(しんかん)とは、古代中国に成立した秦・漢2つの王朝を合わせた呼称。
夏・殷・周と言った古代中国の王朝は実態としては黄河流域にあった「中原」の一部地域を支配する国家であった。
秦と漢の国家体制には違いも存在するものの、皇帝を頂点とする中央集権国家という国家の根幹を引き継ぎ、そのために必要な法制・財政・政策などは秦のものを踏襲した。
国の本字「國」は、□(くにがまえ)の中に「或」であり、□は城壁を表し、内側の或(コク)の「戈」は矛で武力「一」は土地「口」は領土を意味し、字義は「武器を持って城壁(の内側)を守る」です。
では「国」と「中国」は、中国の古典でどう定義づけられているのか?を見てみます。
紀元前4世紀、『孟子』の万章(ばんしょう)下篇に「国(こく)にあるものを市井之臣(しせいのしん)という」とあり、その注釈は「国とは都邑(とゆう)をいうのである」と、いっています。
このように、もともとの「国」は「みやこ」「都城」=「城郭都市」であり、「中国」は、その城郭都市群の中心である「首都」であり、元々の両者の定義には明快な区別もなかったようです。
ただし、都市と都市の間の広大な土地はフリーゾーン(化外の地)ですから、都市間を結ぶ道路なども勝手に作ることができました。
つまり、領土という「面」を繋いで支配したのではなく、「国」とそれらをつなぐ「交通網」という「点」と「線」を支配したのです。
「国」の城門は、日の出とともに開けられ日の入りとともに閉められました。中では市場を中心にあらゆる経済活動が行われ、そこの住民には戸籍が有りました。
言い換えれば、塀の内側だけが中国でそこに住む者だけが中国人だったのです。塀の外は蛮夷の住む化外の地です。
その意味で、岡田英弘は元々の「中国人」とは民族ではなく「文化上の概念」だと指摘します。
前漢の時代には、「国」や「中国」は、もっと広域の意味に使われ始めていました。
「孝武本紀」に、
天下名山八,而三在蠻夷,五在中國。
中國華山、首山、太室、泰山、東萊,此五山黃帝之所常遊,與神會
天下の名山は八つであり、その内三つは蠻夷に在るが、五つは中國に在る
中國の華山、首山、太室、泰山、東萊がそれであり、この五山は黃帝が常に遊び、神と會した所である
天下(人間が住む世界)を「中国」と「蛮夷」に二分し、この五山のある範囲が「中国」であると書いています。その山の位置から判断すれば、「中国」とは、まさに、上の「中原」と呼ばれるエリアに重なる首都長安を中心とした黄河中下流域のことだとわかるのです。
また、「儒教」の世界観では「中国」(天子の支配が直接に及ぶ範囲)は「方一万里」とされていました。
初期(前漢)の『礼記』では、九州(中国)は方三千里とされていましたが、皇帝の支配する都市の所在範囲が広がるに連れ、実情に合わなくなり、前漢を簒奪した王莽(おうもう)は、「古文尚書」の方一万里説を採用するに至りました。
「方一万里」とは「一辺が一万里」の正方形の世界であり、中心となる帝都からはそれぞれの境界まで五千里ということです。「国」が四角の城郭都市だから、そこから四方へ広がった皇帝支配の及ぶ世界「中国」もまた四角形なのです。
正方形の世界ですから中心から境界までの距離は一定ではありませんが、計測したわけではなく儒教の理念を根拠としますから細かいことはどうでもいいのです。
このような宗教的世界観による中国という「領域」の理念と、現代人が勘違いしやすい「国」という漢字の使用が合わさって、古代中国大陸における王朝の「領土」解釈に混乱をきたしているのです。
そこで、勘違いを取り払うためには、もう一度「国」の意味を見つめなおす必要があります。
『日本史の誕生』岡田英弘 より
ここで、郡県制度の本質を説明しよう。封建でないのが郡県で、郡県でないのが封建だなどと、無知なことを言ってはいけない。
「県」は皇帝の直轄都市の意味だが、自然発生的な集落なんかではない。
帝都から送り込まれた軍隊が貿易ルート上の用地で商品の集散地、つまり定期市の立つところを占領して地ならしをし、東西、南北に井桁状に整然たる道路を作り、ブロックごとに木戸をつけ、全体を堅固な城壁で囲む。
場内は全体が常設市場なので、中に入って取引をしようという原住民は、まずこの市場の組員にならなければいけない。
これが「民」というもので、名前を市場の事務所、つまり県庁に登録するとこの資格がもらえるが、「民」たるものは、組合長たる皇帝に対して一定の義務を負う。
組合費として「租」を納めること、市場の設備の維持や修理のために労働力を提供すること、および非組合員の原住民、すなわち「夷」に対して組合員の特権を守るため、自警団に出ること、つまり兵役に服することなどが、そうした義務である。
県が蛮地に建設された中国人開拓者の橋頭堡であるという性格は、いつまでも根づよく残ったので、二十世紀になってもまだ、県の城門の厚い鉄の扉は、日没とともに閉じられ、夜間の外出は重く処罰されることになっていた。
県城の周辺に住んでいたのは、すでに「民」になっていた原住民で、かれらは市場に入って、遠方からきた商人たちと取引するのに、自分たちの土語は通じないから、しぜん帝都の言語を簡単化して、土語の単語とまぜ、一種のピジン中国語(ピジンとは、英語に中国語・マレー語・ポルトガル語をまぜた混合語で、港町で商取引に用いられる)をつくりだした。
これが、今のシナ語の方言の起源である。米軍占領下の日本で発生したパングリッシュ(和製英語)を思いだしてみるがよい。まず、あんなものである。
こうしてシナ語は、市場での取引き用の簡便なことばとしてアジア中に広まり、これを話さない民族はなかった。
もちろん日本人の祖先たちもシナ語を公用語として、隣りの部落と交渉したので、ちょうど今の日本人と韓国人が英語で話しあうようなものであった。
「郡」は軍管区の意味で、郡の「太守」はその司令官であり、行政官ではない。
県と県の間の土地には、まだ皇帝組合に加入しない「夷」がいくらでもいるから、それから「民」を保護するのは、郡の太守の重要な任務である。
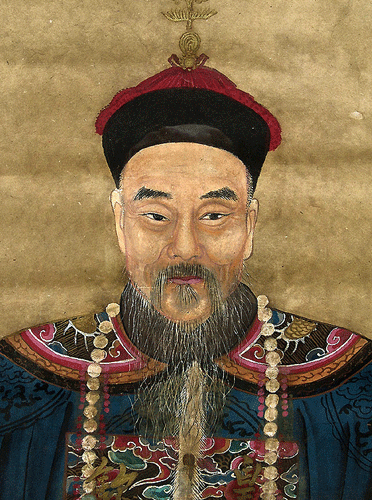
秦の始皇帝の凄いところは「郡県制」を完成させ、36の郡を置き中央集権体制を確立させた点です。
「県」は「直轄」という意味で、それまで「国」と呼ばれていたこれらの都市が「県」になったのです。そして、その上にいくつかの県を監督させる「郡」を置きました。
漢の時代には、この郡の上に13の「州」が置かれました。
ここでも現代人は「いくつかの郡をまとめた州という領域」だと思ってしまうのですが、当初の「州」は行政単位の名称のようなもので、州の刺史(しし)とは郡の監察官であり、特定の治所さえ持たずに担当郡を巡察していたのです。
「県・市(郡)・町」という現代日本の行政区域のようなイメージで、「州・郡・県」を考えるのが間違いで、すべての基本は「県」なのです。
県を監督し守るために軍(郡)を置き、郡の監察組織として州を置いたのです。
監察官たる州「刺史」もまた軍人ですが、後には州長官を指す言葉となり、魏志倭人伝において伊都国の一大率を「刺史のごとくある」と記したのは、彼がそのくらいの大権を持っていたということです。
ちなみに、この「一大率」を「刺史」と比喩したこの記述により、邪馬臺國は少なくとも「九州にはなかった」ということが明確になります。
『後漢書』百官志・州郡条に
孝武帝初置刺史十三人 秩六百石 成帝更為牧 秩二千石
諸州常以八月巡行所部郡國 錄囚徒 考殿最 初歲盡詣京都奏事
孝武帝、初めて刺史十三人を置く 秩は六百石なり 成帝、更(あらた)めて牧と為す 秩は二千石なり
諸州(の刺史)、常に八月を以って所部の郡國を巡行し、囚徒を録し、殿最を考う 初歲に盡く京都に詣りて奏事す
その1州とは、洛陽を含むいわゆる首都圏であり、司隷校尉は所部の郡国のみならず百官への監察権をも持つ別格の存在なのでした。
現在の日本に例えれば、首都東京だけが「都」で、各県警察(県警)が東京だけ「警視庁」と呼ばれるようなものです。
『魏志倭人伝の謎を解く』 渡邉義浩 より
伊都国に置かれた「大率」を「刺史」と表現したのは、伊都国が首都圏に属さないためである。
すなわち、邪馬臺國は九州にはないことが、文献解釈から証明できるのである。
「郡県制」「郡国制」を布いた中国王朝でしたが、皇帝に財をもたらすのは、州でも郡でもなく、県です。皇帝直轄の国(都市)を県と呼ぶのです。
つまり、皇帝の「直轄」(直営)でない「国」は、郡県制に組み込まれないため「国」のままでした。
思うに、陳寿には実力だけでなく、非凡な才があったのでしょう。
ところが、陳寿は、まるで対等の関係にあったがごとき「三国」という表題にし、魏書・呉書・蜀書に書き分けた。これはそれを初めて目にする人には驚き以外の何物でもありません。驚きどころか、怒り心頭に発したかもしれません。
前漢から「邦」に取って代わり「国」は「県」をも含む「領域」を表す言葉になった。
また「郡国制度」によって中原に近い城郭都市(県)と遠方の城郭都市(国)の区別がなされたが、郡県制度の復活により、本来の意味である「国」は郡県制度の外にある蛮夷の都市だけを示す言葉となった。
これまで見てきたように、三国~西晋の時代には「国」という字は、皇帝が支配するべき「天下」の内、「中国」の外「蛮夷の住む世界の都市」だけを指すものでした。
魏・呉・蜀といった王朝を、その「国」と呼ぶことなど、中華思想から見てもありえません。
なんでこんな当然のことを学者諸氏ですら誰一人指摘しないのか?
「書く」というのは、何らかの(政治的など)理由があって、その趣旨に従って自身が述べたいことを書く。どうしても後世に語り継ぎたいことを書く。記録しなければ忘れ去られてしまうおそれがある(と考える)ことを書く。
といった理由があってのことであり、わざわざ記さなくても(当時の人にとっては)当たり前のことは説明の必要が無いから書かないのです。
いったい当時の中国人の誰が『三国志』の「国」を見て「城郭都市」だとか、「都市を含む一地域」だとか、現代人のように「国家」だとか思うでしょうか?
誰が見ても、これ(三国志)は、「三つの“中国の”物語」という意味なのです。「三(中)国志」です。
たとえば、近い時代に書かれた『華陽国志』(かようこくし)は、「華陽」の「地誌」で、この場合の「国」は都市を含む「地域」のこと。
「三つの中国」ということは、同時代に「三人の天子がいた」という事実を指すこととなり、「天子は地上に一人だけ」という中国の世界観に反することとなります。
ところが、その怒りに震える手で三国志を読んでみると、皇帝の伝記である「本紀」を魏書だけに置くなど、見事に魏を正統中国として書き上げていることに驚くのです。
これは、今も昔も中国人が好んで使う「自分を高めるために他者の権威を利用する」または「自分を高めるために相手を(比較において)いったん持ち上げておいて落とす」という手法の典型かもしれません。
「三国」と書いておいて、実は「魏一国」が主役の歴史書。
同時代に、三人の皇帝が、それぞれ三つの「中国」を自称したが、内二つはニセモノでしたよ、という趣旨の書なのです。
敵を高く評価するほど、それに勝利した魏と司馬懿の声価をより高めることになるからです。陳寿とすれば自身の出身である蜀漢を悪くは書きたくないし、むしろ評価すればするほど司馬懿~司馬炎の権威を高めるという一石二鳥のテクニックを活用したのです。
その非凡なセンスと構成力に、張華は「晋書はこの本の後に続けるべき」と称賛したのでしょう。